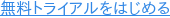働き方改革が叫ばれる中、何をどうやれば良いか悩む経営者層、マネジメント層が多い。
本記事では、「働き方改革」のポイントおよび「36協定」の基本を抑えつつ、実際の現場で「スマートデバイス」を使って働き方改革を行っている実例を紹介する。
1. 働き方改革のポイント
働き方改革のポイントは、平成28年9月27日総理大臣官邸で第1回「働き方改革実現会議」の中での「働き方改革のテーマ」を確認すると以下である。
- 1番目に、同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善。
- 2番目に、賃金引き上げと労働生産性の向上。
- 3番目に、時間外労働の上限規制の在り方など長時間労働の是正。
- 4番目に、雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、格差を固定化させない教育の問題。
- 5番目に、テレワーク、副業・兼業といった柔軟な働き方。
- 6番目に、働き方に中立的な社会保障制度・税制など女性・若者が活躍しやすい環境整備。
- 7番目に、高齢者の就業促進。
- 8番目に、病気の治療、そして子育て・介護と仕事の両立。
- 9番目に、外国人材の受入れの問題。
これらの「働き方改革のテーマ」の中で、「スマートデバイス」を活用することでどんな効果が期待できるだろうか?
例えば「スマートデバイス」を活用することで、仕事の情報を「スマートデバイス」の中に集約したり、電子報告書機能を活用することで生産性の向上が期待できる。またいつでもどこでも「スマートデバイス」があれば仕事ができる状態になればテレワーク等の柔軟な働き方の促進を後押しすることに期待が持てるだろう。スマートデバイスで利用することができる、営業支援システムやSFA、CRMを活用することで、様々な業務の効率化が可能となる。また、クラウドサービスを活用することで、自社でシステムを抱える必要がなくなればイニシャルコストを下げるのみならず、ランニングコストを下げて利用することができる。
あるいは、「スマートデバイス」によって、複雑な操作が必要なく業務を行うことができれば、高齢者の就業促進や外国人材の活用にも寄与し、生産性向上から「働き方改革」に繋がる。
次に、「働き方改革」の関連テーマの「36協定」についてみていこう。
2.「36協定」とは何か?
36協定は正式には、「時間外・休日労働に関する協定届」という。この協定のことを労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定」と呼ばれている。
チェックポイントは、「時間外労働をさせる場合の限度時間」である。
限度時間は、労働省告示「労働時間の延長の限度等に関する基準」により、その上限が定められており、1ヶ月の場合は45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間)、1年の場合は360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は320時間)と規定されている。
※以上抜粋
厚生労働省東京労働局
厚生労働省の調べでは、36協定・特別条項付36協定を締結している事業場が55.2%で、36協定で定める延長時間は限度基準(月45時間・年360時間)に集中化する傾向がわかった。
※以上抜粋
厚生労働省第104回労働政策審議会労働条件分科会資料
「働き方改革」によって残業時間を減らし、ワークライフバランスを保ちつつ健全・健康な社会を目指すという「スローガン」には賛同するが、「36協定」の実情からみると残業時間削減や生産性向上の「現実」は厳しいものがあるようだ。
このように「理想と現実」のギャップがみえる状況の中、例えば「スマートデバイス」を活用することで「働き方改革」に取り組む企業がある。次項で実例を説明する。
3. スマートデバイス活用による働き方改革活用事例

「スマートデバイス」を活用することで、どんな業務が効率化できるだろうか?
例えば、「スマートデバイス」の利便性を活かして、いつでもどこでも仕事が出来るという観点に着目すると、毎日のチーム間の連絡や報告書業務を効率化することなどからはじめると導入し易いし、具体的に帰社のための「残業代」がなくなるという点でROIを出し易いだろう。
様々な可能性が考えられるが、ここでは以下のポイントに絞ってみていく。
- ■ケース1 電子報告書機能を活用することで、直行直帰型の働き方へ改革
- ■ケース2 建設施工現場の写真管理の効率化による働き方改革
- ■ケース3 リモート勤務をITクラウドで実現することによる働き方改革
■ケース1 電子報告書機能を活用することで、直行直帰型の働き方へ改革
一日業務を行った後、「報告書」作成や「報告業務」を行うために、帰社する営業マンや保守スタッフ、ラウンダー業務スタッフは多い。
この報告書業務を「スマートデバイス」の電子報告書機能を活用することで、効率化し直行直帰型のワークスタイルに「働き方改革」を行い成功させた事例がある。営業などの外で働くワークスタイルの営業支援にも同様の効果が期待できる。
また報告書を位置情報と組み合わせることで、エビデンス情報となる。
このように位置情報と電子報告書によって、会社とエンゲージメントを高めながら業務改革を行うことができる。
■ケース2 建設施工現場の写真管理の効率化による働き方改革
オリンピックが開催される2020年に向け、国内の建設市場は好調な受注環境を背景に業績を伸ばす企業が目立つ中、建設業界全体でも人材不足が課題となっている。
そのような背景の中「スマートデバイス」の活用によって、人材不足、生産性向上、高齢者・外国人登用などの取り組みで成果出している事例を紹介する。
位置情報の活用によって、現場の写真を地図上にマッピングすることで仕分け工数、検索工数が低減することができる。
また自分の現在位置に近い自社物件、新規見込み物件、OB物件の確認も、スマートフォン上で容易に行うことができるため、「ついでの一件」訪問も容易である。
このことで会社とのエンゲージメント、顧客とのエンゲージメントが高まる。
①某ハウスメーカー様 : -「残業時間」と「工事写真仕分け業務」を削減-現場の「エンゲージメント」を高める。位置情報活用SFA事例。

②シャプラ・インターナショナル株式会社様 : 報告書の「写真機能」は、「エビデンスとして重宝しています」〜言葉の壁を超えて外国人でも使える位置情報活用SFA〜
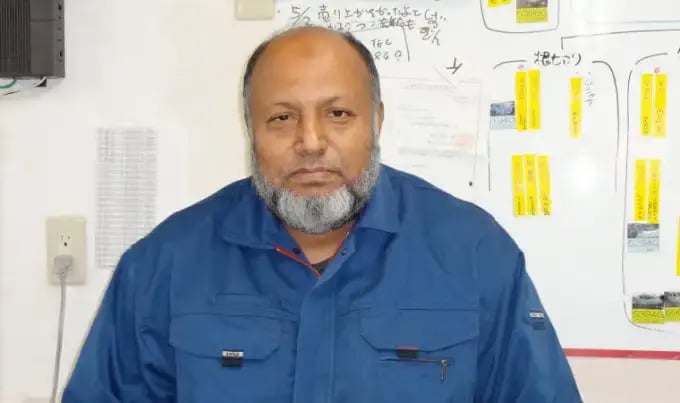
■ケース3 リモート勤務をITクラウドで実現することによる働き方改革
現代人は忙しい。
特に家庭において負担がかかり易い世代である子育て世代、介護世代に対して「リモート勤務」等によって柔軟に働き易い環境を整備することは急務である。
しかしながら「リモート勤務」を実施するためには、会社と社員の「信頼」の醸成が必須である。
そのような環境の中、「スマートデバイス」を活用し、どこで何をしているかの情報を共有する環境を整備することでお互いの「エンゲージメント」を高めることができる。
①レッドフォックス:「働き方改革」をITクラウドで実現した最新事例 「cyzen(サイゼン)」のスマートフォン機能活用 在宅勤務を見える化し社員のリモートワークを推進

4. 3つのポイント
以上、事例を交えて「スマートデバイス」を活用した「働き方改革」についてみてきたがいかがだったであろうか?
実際の現場で「スマートデバイス」を使って働き方改革を行うための要点について説明する。
■ポイント1 As is to be
現状把握とゴール設定が重要である。
「スマートデバイス」を活用すると、今の業務の何の課題に対して圧倒的に成果が出そうかゴールを設定することが重要である。
ゴールがスタッフの直行直帰型スタイルの確立なら、会社で行っている業務の細分化が重要だ。
具体的に何の業務にどのくらいの時間がかかっているのか?それは社内で行う必然性がある業務なのか?何がボトルネックになっているのか?など課題を特定するための精査が必要である。
その上で、「スマートデバイス」で置き換えることが可能か考える。
■ポイント2 現場業務をシステムに合わせない
端的に言えば、現状行っている業務を「スマートデバイス」活用のために合わせるべきではない。この姿勢が新しいことを実行する上で重要である。
具体的には、「報告書作成業務や報告業務」を「スマートデバイス」の活用で電子化するなら、「報告書のフォーマット」は既存のまま置き換えられることが望ましい。
そのためには、現状の業務にあわせて柔軟に変化するシステムを選択するべきである。
また「報告書業務」の質が担保され、正しい報告がなされているかどうかチェックできることも重要である。この時に正しいかどうかの判断として、位置情報のチェックイン情報等とひもづけて電子報告書を活用したり、作業ステータスを報告することができればお互いのエンゲージメントが高まるであろう。
「報告業務」が「スマートデバイス」活用で効率化されたとしても、今までのように金曜日の夜にまとめて報告書を入力するような運用では意味が無い。
スムーズな運用を促すためにも位置情報の活用や自動化が重要となってくる。
■ポイント3 運用が容易
運用が容易とは2つの視点で必要である。
第一に、実際の働く人の「運用が容易」であること。「スマートデバイス」を活用しても、複雑なインターフェイスや操作が必要となると現場の働く人の不満になり、使われなくなってしまう。
次に、運用者視点での「容易さ」だ。
「スマートデバイス」活用のために、莫大な準備が必要であったり、膨大なデータをインプットしないと運用をスタートできないようになると、最初の段階で躓いてしまい結果が運用に乗らなくなる。
会社の規模や利用人数にもよるが、一般的に「運用」をスタートして、最初の3日、最初の3週間、そして3ヶ月間が重要である。
運用開始から最初の3日のうちには設定作業が終了して現場でも使える状態になっているようなスモールスタートを切れることが望ましい。
3週間までに小さくてもよいから、「成功事例」があることが望ましい。
3ヶ月間で「スマートデバイス」活用・利用状況、そこからの課題改善策などを行うと良い。
以上ポイントについて述べた。
あなたの会社でも「働き方改革」を推進する上での「スマートデバイス」活用を検討されることをお勧めする。